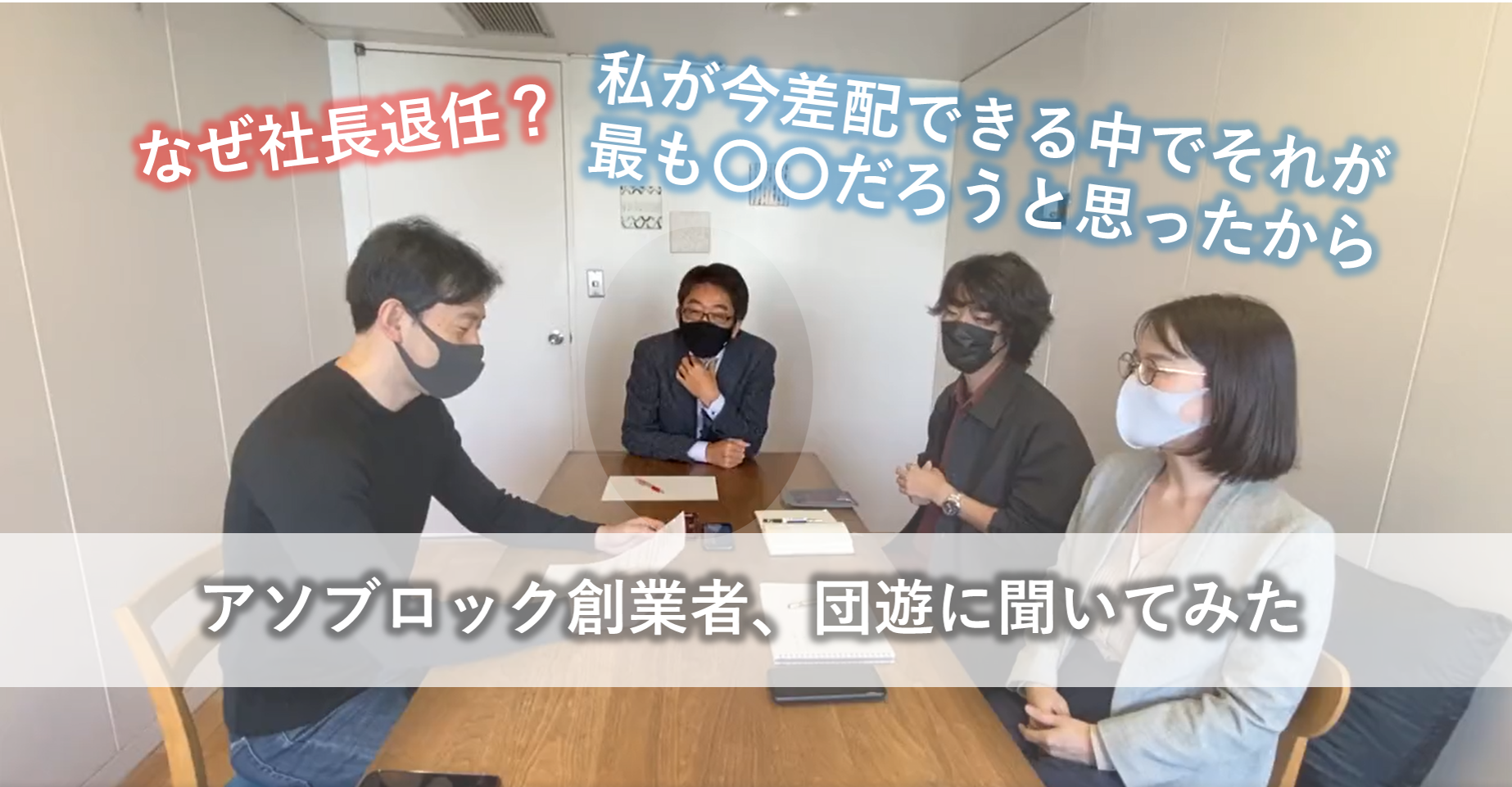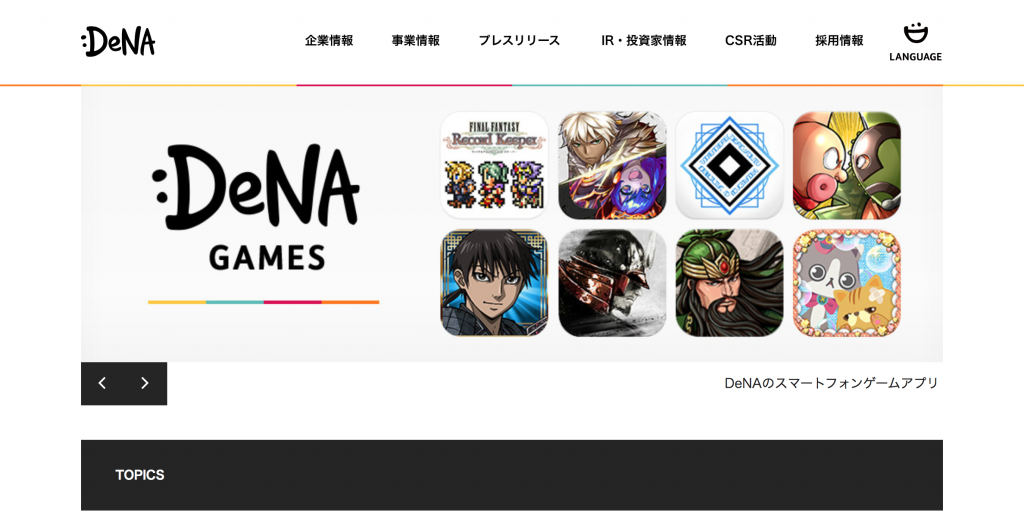ものづくりに限らず、新しい事業やサービス、商品や仕組み、制度を生み出そうとするとき、
それらをより価値の高いものにするために考えるべき要素とは何かについて考えました。
これは私がつねに意識しているものであり、
一般的かつ創造にたずさわる者としては見落としてはならない重要なものではないかと思っています。
1.ビジネス
新しいものを生み出すことは、発信者の発想やアイデアによってその創造プロセスがスタートします。それは時代の要請である時もあれば、ある意味でエゴイスティックな自己満足を出発点としたものであることもあります。いずれにせよ、それらが社会で生き残り、人々に求められるものであり続けるためには、ステークホルダーの投資や購買行動によって持続的に運用することが可能であり、収支が成立するものでなければなりません。どんなに顧客や消費者がそのサービスや商品を満足度高く受け取ったとしても、その対価が正当でなかったり、その価値に比して高価すぎものは、発信者と受け手の関係性が崩れており、継続することが難しくなってしまいます。
2.デザイン
デザインとは根本的な立ち位置を社会に横たわっている問題に発端を求めるものではないかと思います。そして、その問題解決を考えることそのものがデザインです。よく絵を描いたり、色を塗ったりすることがデザインとされることがありますが、それは問題解決の手法のひとつにすぎません。創造プロセスの中で、問題意識が生まれたり、そもそもの創造物の出発点が何らかの問題意識に始まっている場合、その問題解決に対し、何を紐解き、どのように問題に紐づけられたパーツを再構築し、新しいストーリーをいかに描き、目的達成にどう導くのか。この企画・設計のすべてがデザインの取り組みではないかと思います。
3.アート
アートはデザインに対し、より自己の中に発端を求めるものであり、なぜ?どうして?で説明出来ないような発信行動はすべてアートであると言ってよいと思います。逆に言えば他者や社会の問題解決を思考しているのに、なぜ?どうして?で説明できないような問題解決手法はそれはその時点で、デザインでなくアートの領域だということです。アートは非常に刺激的で生命力にあふれています。政治や地域社会がアートを求めるような機会が世の中には時折見受けられますが、その根源にはアートが持つ壁を突き破っていく力強いパワーや変化に富んだ刺激にその目的があるのではないかと思います。
4.テクノロジ
情報化社会の発達の中で、創造に欠かせないものとなっているのがテクノロジです。テクノロジとは、原理や法則を利用して、よりよい創造成果を得られるために工夫をすることそのものであり、コンピュータやロボット、それらを形作る技術のことです。テクノロジは次項のコミュニケーションと密接に関わりますが、どの技術や手法を選択するかで、創造プロセスが飛躍的に推進することがあるため、その選択にはとても注意が必要になってきます。
5.コミュニケーション
どういった形でユーザー・消費者とコミュニケーションをおこなうかについてはその重要性は筆舌に尽くしがたいものがあります。どの場で、どのようなメディアを用いて、いつ、誰に、何を伝えるのかについてデザインがなされた結果、どのような意志の疎通を行うのか、心や気持ちをどのように動かし、どう理解してもらうのか?どう感じてもらうのか?このコミュニケーションの描き方は多様であるからこそ、疎かになりがちなものです。
これらのことはものづくりの開発者のみならず、企業や組織においてマネジメントをおこなうリーダーやプロジェクトを組成し推進する人たちにとって有効な視点であり、思考が停滞した時にひらめきや発見をもたらす可能性のある視点ではないでしょうか。